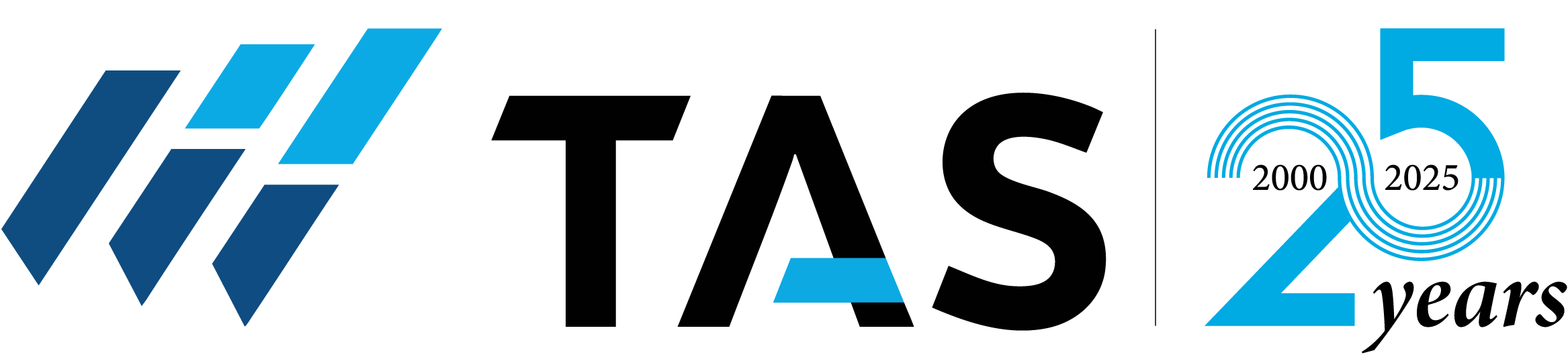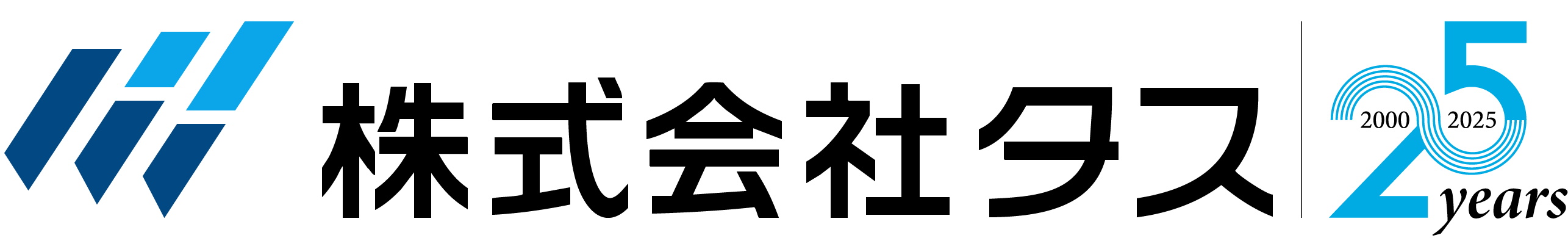金融政策と住宅市場 ― 政策金利上昇がもたらす影響
清水千弘
一橋大学大学院教授・都市空間不動産解析研究センター長
- はじめに
先日の日本銀行の政策決定会合では、政策金利の引き上げを支持する委員が二名いたことが注目されている。日銀内部では、これまで物価目標や賃金上昇の動向を慎重に見極めてきたが、最近のデータで企業の価格設定行動や賃金の上昇が予想よりも堅調であるとの認識が広まりつつある。海外の原材料価格の高止まりや輸入コストの上昇も、物価を下支えする要因として意識されており、これらが日本のインフレ見通しを引き上げる可能性をめぐって議論が活発化してきた。
中でも、賃金が上がってもそれが消費者物価にどの程度転嫁されるか、企業がコスト上昇を価格へ反映できる構造になっているかという「価格転嫁力」の観点が、利上げ支持の委員の主張の核をなしている。一方で、消費の冷え込みや輸出・投資とのバランス、景気の下振れリスクを懸念する慎重派も根強く、政策決定は一致を見ていない。この二人の賛成は、利上げを将来の選択肢として強く市場に印象づけるものだ。
今後政策金利は、賃金と物価の見通しが一定の基準を満たすことを条件に、段階的な引き上げを進めていく可能性が高い。具体的には、現在の水準(約0.5%前後とされる無担保コール翌日物利率など)から、2025年~2026年にかけて0.75%、あるいは1.0%近くへの上昇を想定する見方が出てきている。
ただし、歩みは緩やかであり、利上げの速度やタイミングは賃金の伸び、予想物価上昇率、国際情勢、為替や輸入物価の動きに左右されるだろう。
米国ではインフレおよび利下げ圧力の中で政策金利の引き下げが徐々に議論されているが、それとは対照的に日本は、構造的な賃金上昇と物価定着を図るために、今なお金融引き締めを検討する局面にある。日本にとっては、物価の「上昇」すなわちインフレを単一の目標とするだけでなく、賃金の実質上昇を伴い、生活者の購買力が損なわれない形での物価上昇をどう実現するかが問われている。利上げをしても、それが賃金上昇や生産性改善と連携しないならば、景気を害し、住宅市場を含む資産市場に逆風をもたらす可能性がある。そのため、政策金利上昇の是非、タイミング、ペースについては、極めて慎重な判断が必要である。 - 住宅価格と金融政策の基本的枠組み
住宅価格を含む不動産価格は、一般に「将来収益の割引現在価値」として説明される。家計が住宅を購入する際に期待するのは、居住サービスの便益や将来の資産価値であり、それを現在の価格に織り込む。ここで割引率の大きな決定要因となるのが金利である。したがって、政策金利が上昇すると、将来収益を割り戻す割引率が高まり、理論的には住宅価格を押し下げる方向に働く。
しかし、住宅市場は単純な数式では説明できない。金融政策が住宅価格に与える影響は、いくつかの経路(チャネル)を通じて現れるため、その効果は時期や国の状況によって大きく異なる。以下では、政策金利上昇のメカニズムを複数の視点から整理する。
最も直截的なのは、住宅ローン金利への波及である。これは「金利チャネル」と呼ばれる。政策金利の引き上げは短期金利を押し上げ、やがて長期金利にも影響を及ぼす。長期固定金利の住宅ローンを利用する場合、その金利が上昇すれば毎月の返済負担は増し、家計の住宅購入意欲を抑制する。可変金利型ローン利用者にとっては、返済額の増加が直ちに家計の消費余力を圧迫し、住宅市場全体の需要を冷え込ませる。
この金利チャネルを通じた影響は、特に住宅需要が旺盛な局面において顕著となる。価格高騰期には家計が高額の借入れをして住宅を取得するが、金利上昇はその返済負担を重くし、需要の抑制要因となる。結果として、住宅価格の上昇が鈍化し、場合によっては価格下落をもたらす。
また政策金利が上昇すると、国内通貨建て資産の利回りが相対的に高まるため、海外から資本が流入し、円高が進む傾向がある。円高は輸出産業にはマイナスだが、住宅市場には複雑な効果をもたらす。一方では、円高によって外国人投資家にとって日本の住宅資産は相対的に割高となり、海外資金による住宅投資が抑制される。他方で、円高に伴い輸入物価が低下し、建設資材のコスト低下を通じて住宅供給コストに下押し圧力をかける可能性もある。為替を媒介とするこの効果は、住宅価格に対して双方向的に働く。これを「為替レートチャネル」と呼ぶ。
このような効果は、直感的にも理解がしやすいであろう。 - その他のチャネル ― 投資家行動の変化
低金利環境では、金融機関や投資家は安全資産で十分な利回りを得られないため、リスクの高い資産(株式や不動産)に資金を振り向ける傾向が強まる。逆に政策金利が上昇すると、安全資産の利回りが改善し、不動産投資への資金流入は鈍化する。この結果、不動産市場への投資需要が減少し、住宅価格の下押し要因となる。ただし、リスクテイキング・チャネルの影響は投資家心理や市場環境によって左右される。株式市場が不安定な場合には、政策金利上昇にもかかわらず不動産が相対的に安全な資産とみなされ、投資が続く可能性もある。
また、金利上昇は借入れコストを引き上げ、家計や企業のバランスシートを悪化させる。担保価値としての住宅価格が下がれば、借入可能額も減少し、さらに住宅需要を抑制する。逆に住宅価格が下落すれば、担保価値が減少して金融機関の貸出態度も厳格化する。この悪循環が「フィナンシャル・アクセラレーター」と呼ばれる現象である。
日本のバブル崩壊後に見られたように、住宅価格の下落と信用収縮が相互に強化し合うことで、経済全体が長期停滞に陥る危険性がある。政策金利の上昇は、このサイクルを誘発するリスクを孕んでいる。
さらに、金融政策は住宅価格だけでなく、賃貸市場にも影響を及ぼす。家賃はCPI(消費者物価指数)の中で25〜30%を占める重要な項目である。しかし、歴史的に見ると、住宅価格が急騰・急落しても、家賃の変動は緩やかである。これは、家賃が契約制度や供給制約に強く影響され、短期的には需給の変化を反映しにくいためである。政策金利上昇によって住宅価格が下がっても、家賃への影響は限定的かつ時間をかけて現れる。 - 金融政策の限界と構造的要因
政策金利の上昇が住宅市場に与える効果は無視できないが、それだけで住宅市場を完全にコントロールすることはできない。日本の長期デフレ期に示されたように、金融政策は万能ではない。人口減少や高齢化によって住宅需要そのものが縮小していれば、政策金利の上下動だけでは市場の趨勢を覆せない。逆に、都市再開発や規制緩和によって住宅供給が増加すれば、金利上昇下でも住宅価格が一定の水準を維持する可能性がある。
米国のサブプライムバブル期は、低金利が住宅市場を過熱させ、過剰融資と価格高騰を引き起こした典型例である。その後の政策金利上昇は住宅ローン破綻を誘発し、世界的金融危機をもたらした。欧州諸国でも、低金利期の住宅価格上昇と、その後の金利上昇による急落が観察されている。これらの経験は、政策金利上昇が住宅市場に与える影響の大きさと、その不均衡の危険性を物語っている。 - おわりに
政策金利の上昇は、住宅市場に対して複数の経路を通じて影響を与える。金利負担の増加を通じた直接的効果、為替変動を通じた外部資金の動き、投資家行動の変化、バランスシートの悪化と信用収縮など、その影響は複雑かつ多面的である。理論的には住宅価格を押し下げる方向に働くが、その実現度合いは経済環境や人口動態、制度的要因に左右される。
したがって、金融政策だけで住宅市場を安定させることは難しい。むしろ都市政策、住宅供給政策、社会保障政策などとの総合的な組み合わせが不可欠である。住宅は生活の基盤であると同時に資産でもある。その二重性を踏まえ、政策金利の動向を正しく理解しつつ、住宅市場の安定と経済の持続的成長を実現する枠組みを構築することが求められている。