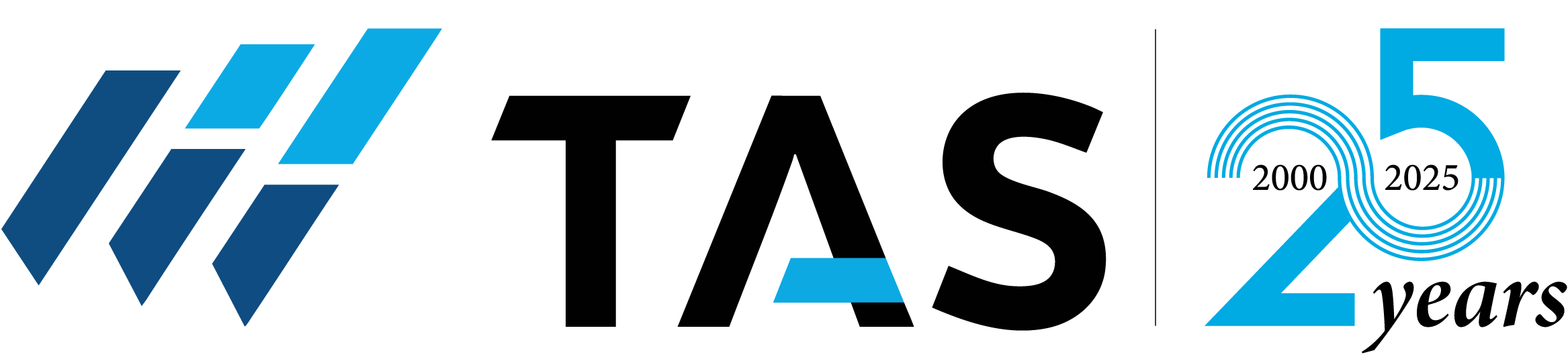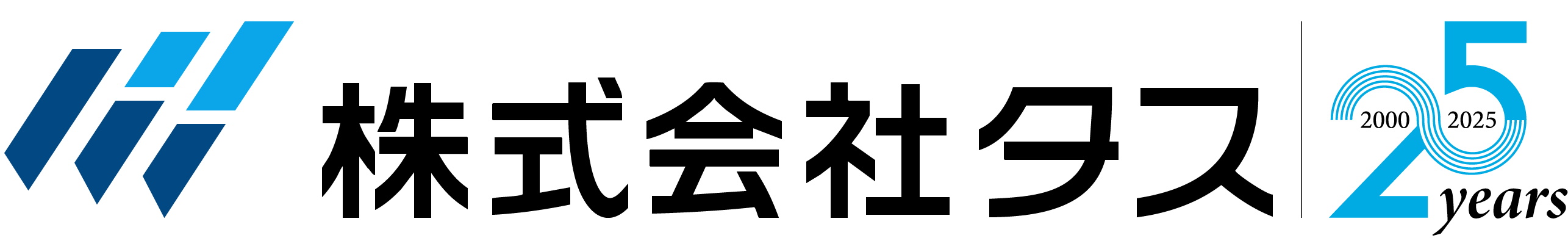第一章 東京のマンション価格はバブルか?
今回から、一橋大学大学院教授である清水千弘先生からご寄稿いただいた、東京における住宅価格の高価格化構造をテーマとしたコラムを連続で配信します。
分割しての配信であり学術的側面も含みますが、非常に興味深い内容となっていますので是非最後までご覧ください。
以下は全体の章立てとなります。
第一章:東京のマンション価格はバブルか?
第二章:ユーザーコスト理論・厚生一貫的指数理論・バブル必然理論の統合
以降の章については、順次追加・掲載予定となっています。
――――――――――――――――――――――――
第一章 東京のマンション価格はバブルか?
清水千弘
一橋大学大学院教授・都市空間不動産解析研究センター長
日本の住宅価格の動向は、経済・社会・政策・心理の交錯する複雑な現象である。近年、東京圏における住宅価格の上昇は著しく、2025年時点で東京都区部の新築マンション平均価格は1億円を超えた。その一方で、地方都市や農村地域では住宅ストックが余剰化し、空き家は全国で900万戸を超えている。こうした二極化を、単純に「バブル再来」とみなす言説が依然として流布しているが、その説明はもはや十分ではない。むしろ今日の住宅価格の高止まりは、マクロ経済的、制度的、人口的、そして心理的な諸要因が重層的に作用した構造的現象として理解されるべきである。
住宅価格の上昇が一時的な投機の結果であるならば、過去のバブル崩壊のように急速に下落するはずである。だが、現実にはそうはなっていない。住宅価格はリーマン・ショック後も長期的上昇傾向を維持し、特に2013年以降のアベノミクス期以降、再び高騰した。このような持続的上昇をもたらす基盤は何か。それは、①超低金利の定着による資金コストの恒常的低下、②人口の再集中と世帯構造の変化、③都市再開発を中心とする制度的枠組みの転換、④資産保有に対する社会心理の変化、そして⑤政府の政策的選択である。本章では、まず日本の住宅価格問題を歴史的文脈の中で再構成し、1980年代から2020年代に至るまでの政策転換の連続性を整理する。
1980年代の日本経済は、急速な国際環境の変化の中で構造的転換を迫られた時代である。
1970年代の高度成長の終焉後、日本は輸出主導型経済を軸に世界経済の中で競争力を維持していたが、1980年代に入ると、米国との貿易不均衡が深刻化した。1985年のプラザ合意は、ドル安・円高を通じてこの不均衡を是正するための国際合意であったが、その副作用として日本国内では過剰流動性が生まれた。当時、政府と日本銀行は円高不況を回避するために金融緩和を実施し、低金利政策を続けた。この金融緩和が土地・不動産市場への資金流入を加速させた。とりわけ、土地は担保価値の上昇を通じて信用創造の媒介となり、地価の上昇がさらなる融資を呼ぶ「自己増殖的プロセス」が形成された。
このプロセスは、1980年代後半に顕著な資産バブルを生む。土地・株式などの資産価格が高騰し、特に東京の地価は数年で数倍に達した。背景には金融自由化の進展もあった。
1980年に外国為替取引の自由化、1983年の銀行法改正、1985年の金融制度調査会答申によって、金融機関の競争が激化し、貸出拡大が進んだ。この金融自由化と低金利政策の組み合わせが、資産市場を急速に膨張させたのである。
また、1980年代の住宅政策は、土地政策と一体で展開された。土地を「国民共有の資源」と位置づけた政府は、地価上昇を抑えるために地価税や総量規制を導入したが、それは一方で金融機関の担保主義と矛盾した。1987年の不動産融資総量規制は、表面的には過熱抑制策であったが、実際には地価の上昇が止まらず、むしろ市場の歪みを拡大させた。1989年には消費税導入、同年末には日銀が公定歩合を引き上げ、金融引締めに転じたが、すでに形成された資産バブルはあまりに巨大で、引き締めの効果は遅れて現れた。
1991年、バブル崩壊。土地・株式価格の急落は、金融システム全体を揺るがせた。銀行は巨額の不良債権を抱え、企業のバランスシート調整が始まった。政府は金融システム安定化のために公的資金注入を行い、不良債権処理特別法を制定した。同時に、1992年には「土地基本法」を制定し、土地を投機の対象から社会的資源として位置づけ直した。これが、土地政策の根本的転換点となった。地価は1990年代を通じて下落を続け、東京の商業地価格はピーク時の3分の1にまで低下した。
この時期の金融政策もまた、急速な引き締めから緩和へと転換した。1995年にはゼロ金利政策が導入され、以後、低金利が恒常化する。しかし、デフレの進行により実質金利はむしろ高止まりし、企業投資は停滞した。政府は景気刺激策として公共事業や住宅取得減税を拡大したが、経済の本格回復には至らなかった。この「失われた10年」、実際には20年以上にわたる停滞は、住宅市場の制度構造を大きく変えた。
まず、住宅金融公庫の役割が変わった。従来は「持ち家促進」を目的に低利融資を提供していたが、1990年代後半以降、財政負担削減と市場化を目的に民営化が進んだ。2007年には「住宅金融支援機構」が発足し、民間ローンと証券化を組み合わせた仕組みが導入された。これにより、住宅ローン市場は資本市場と直結し、金利変動や金融政策の影響を直接受けやすくなった。また、住宅市場の供給側では、建築基準法改正(1998年)によって耐震・環境性能が重視され、都市再開発事業の手続きが簡素化された。これが後の2000年代の「再開発ブーム」につながる。
2000年代に入ると、地価は底打ちし、金融システムの再生とともに都市再生が始まる。2002年の「都市再生特別措置法」は、老朽化した都市インフラの更新と民間投資の促進を目的とし、容積率緩和や税制優遇を通じて再開発を容易にした。以後、東京では六本木ヒルズ、汐留、丸の内、虎ノ門など、大規模な再開発が相次いだ。この時期、日本経済はゼロ金利政策下でデフレを克服できなかったが、都市部の地価だけは上昇に転じた。住宅価格の上昇は経済回復の指標として歓迎され、政府もこれを成長戦略の一環とみなした。
2010年代に入ると、アベノミクスによる大規模金融緩和が実施された。量的・質的緩和(QQE)は、マネタリーベースを飛躍的に拡大し、長期金利を実質的にゼロに固定した。これが住宅ローン金利を史上最低に押し下げ、住宅価格の上昇を再加速させた。同時に、国家戦略特区制度が導入され、都市再開発がさらに促進された。この時期の特徴は、再開発が単なる経済政策ではなく、人口減少時代の「都市の生存戦略」として制度化されたことである。
そして2020年代。コロナ禍を経て在宅勤務が普及し、一時的に都市集中が緩むとの見方もあったが、実際には東京圏の人口は再び増加している。低金利は継続し、円安とインバウンド需要の回復によって外国資本が流入した。都市部では、脱炭素化・スマートシティ構想・再エネ建築など、持続可能性を意識した再開発が進行している。その結果、住宅価格は再び上昇し、1980年代のピークに匹敵する水準に達した。
このように見てくると、日本の住宅価格は、1980年代のバブル形成、1990年代の崩壊と再構築、2000年代以降の再開発という一連のプロセスを経て、金融・制度・心理が長期的に結合した「構造的高価格均衡」を形成したことがわかる。今日の住宅価格上昇は、過去の政策選択の延長線上にある。金融緩和、都市集中、再開発推進――これらはいずれも1980年代以降一貫して続いてきた政策パラダイムである。
Shimizu(2025), “Beyond the Bubble: Structural Drivers of Tokyo’s High Housing Prices”この長期的な政策・制度・人口・心理の相互作用を明示的にモデル化し、東京の住宅価格の高止まりを投機的バブルではなく、低金利社会における合理的な均衡現象として再解釈することであった。本稿は、同論文を解説することを目的とする。第一にユーザーコスト理論とバブル必然理論を統合し、価格・家賃・金利・期待の統合的方程式を提示する。第二に、1986年から2025年までの東京住宅市場データを用い、長期共和分分析とVECM推計を通じて価格主導型調整メカニズムを実証する。第三に、再開発・制度改革・金融政策の変化を歴史的に整理し、それがどのように住宅市場の構造的均衡を形成したかを検討する。第四に、国際比較を通じて日本特有の制度的特徴を明らかにする。そして最後に、政策的含意として、「価格を下げる」政策から「期待を安定させる」政策への転換を提言する。
この研究の基礎仮説は明確である。住宅価格の上昇は、バブル的逸脱ではなく、低金利、人口構造、都市政策、社会心理の相互作用によって形成された長期的均衡である。その均衡を理解しない限り、持続可能な住宅政策は設計できない。
本章では問題の所在を提示したが、次章以降では理論的枠組み、実証分析、制度史的考察を通じて、この仮説を精緻に検証していく。