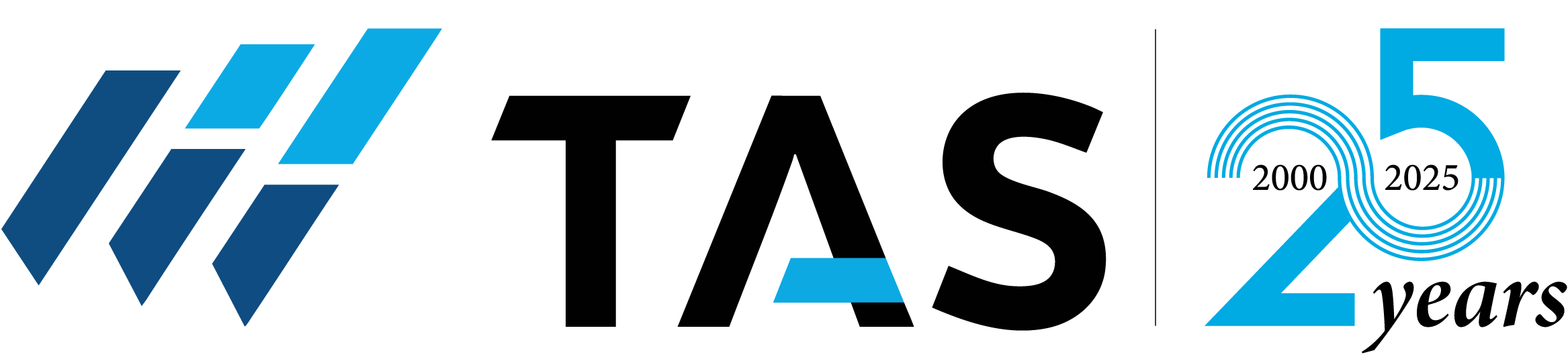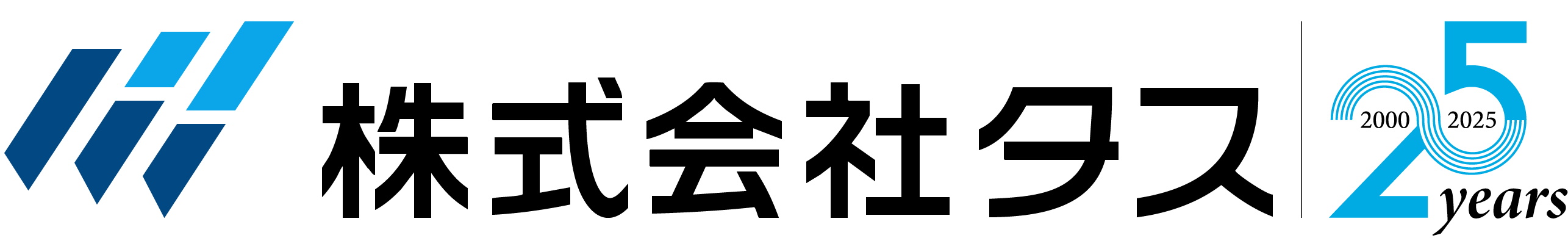第二章 ユーザーコスト理論・厚生一貫的指数理論・バブル必然理論の統合
前回に引き続き、一橋大学大学院教授である清水千弘先生からご寄稿いただいた、東京における住宅価格の高価格化構造をテーマとしたコラムを連続で配信します。
分割しての配信であり学術的側面も含みますが、非常に興味深い内容となっていますので是非最後までご覧ください。
以下は全体の章立てとなります。
第一章:東京のマンション価格はバブルか?
第二章:ユーザーコスト理論・厚生一貫的指数理論・バブル必然理論の統合
以降の章については、順次追加・掲載予定となっています。
――――――――――――――――――――――――
第二章 ユーザーコスト理論・厚生一貫的指数理論・バブル必然理論の統合
清水千弘
一橋大学大学院教授・都市空間不動産解析研究センター長
日本の住宅市場を理解するうえで最も重要な前提は、「住宅価格とは何によって決まるのか」という根本的な問いに対する答えを明確にすることである。住宅は、家計にとって単なる「モノ」ではなく、時間の中に埋め込まれた存在である。今日住むための場所であると同時に、将来の資産価値を担保する「金融的財産」でもある。この二面性こそが住宅の本質を形づくっており、住宅価格の変動を理解するには、居住というフロー(流れ)と、資産というストック(蓄積)を同時に捉えなければならない。
住宅を所有するという行為は、毎年、ある経済的な費用を発生させる。ローンの利息、減価償却、固定資産税、維持管理費、そして将来の価格変化への期待がそれである。これらを総合した「年間所有コスト」を、経済学ではユーザーコストと呼ぶ。このユーザーコストは、家賃の代替として機能する。もし住宅を借りるならば支払うべき家賃を、自ら所有することで内部化しているという考え方である。したがって、住宅の市場価格は、このユーザーコストと家賃の関係によって決まる。金利が低下すればローン利息が減り、ユーザーコストが下がる。それに対して家賃があまり下がらない場合、住宅を所有する方が経済的に有利となるため、購入需要が高まり、価格は上昇する。
この理論の意義は、住宅価格の上昇を「非合理的な熱狂」とみなすのではなく、家計の合理的な行動の結果として説明できる点にある。日本のように長期にわたり低金利が続き、税制上も住宅所有を奨励する政策が取られている国では、住宅価格の上昇は投機ではなく、合理的な適応である。つまり、経済主体が将来にわたって居住サービスを享受しようとする際、割引率が低ければ低いほど、現在の住宅の価値は高まる。これが長期にわたる価格上昇を理論的に支える基礎である。
ただし、住宅は投資財であると同時に消費財でもある。人は住宅を買うことで「住む」という便益を得る。したがって、住宅価格の変化が生活の豊かさや満足度にどう影響するかを考えるためには、厚生の観点を組み入れる必要がある。ここで重要になるのが、厚生一貫的指数理論である。経済学者のブリティッシュコロンビア大学のアーウィン・ディーワート教授は、価格指数を単なる物価の変化ではなく、人々の生活水準を維持するために必要な費用、すなわち「生活費関数」として定義した。住宅の価格をこの観点から見ると、価格の上昇は単なる「値上がり」ではなく、生活の便益がどのように変化したかという視点から評価されるべきものとなる。
ディーワートと筆者(2020)は、住宅所有者が享受する「帰属家賃」、すなわち自分の家に住むことで得られる居住サービスの価値を測定するための理論を構築した。この理論によれば、住宅価格は単に市場取引の結果ではなく、家計が生活の満足度を最大化するために選択する最適な価格である。住宅の価値は、快適性、安全性、立地条件、環境などの要素を総合的に評価した結果として形成される。したがって、住宅価格の上昇は、家計がより高い生活の質を求め、居住サービスの価値を重視する傾向を反映した「厚生的選好の表れ」とみなすことができる。
この視点をさらに拡張すると、住宅市場における価格上昇は、生活水準を維持するための「必要条件」として生じている場合があることがわかる。住宅を取り巻く社会環境が変化する中で、家計が一定の生活の質を保つために支払うべきコストが高まる。たとえば、都市の安全性、教育環境、交通アクセスなどの価値が上がれば、同じ「暮らしやすさ」を維持するために支払う価格も上昇する。これが厚生一貫的な意味での価格上昇である。単なる市場の高騰ではなく、人々が選択する生活水準の反映なのである。
このように、ユーザーコスト理論と厚生一貫的指数理論を組み合わせると、住宅価格の上昇は「金融的合理性」と「厚生的合理性」の交点に位置することがわかる。前者は金利や期待を通じた資本の論理であり、後者は生活の質を通じた人間の論理である。この二つが同じ方向に作用する時、住宅価格は長期的に上昇しやすくなる。低金利のもとで将来価値が高まり、同時に都市再開発や生活環境の改善によって居住便益が高まれば、価格が上昇するのは自然な結果である。
こうした状況を経済理論的にさらに一般化したのが、近年の「バブル必然理論」である。「バブル必然理論」では、資本主義経済において金利が経済成長率を下回ると、資産価格の上昇は避けられないとする。すなわち、社会全体の成長が鈍化し、資本収益率よりも低い金利が持続する環境では、投資資金が実体経済よりも資産市場に流れることは、投機ではなく合理的な資源配分である。これが彼らのいう「バブルの必然性」である。住宅市場にこの理論を適用すれば、長期的な低金利が続く日本では、住宅価格の上昇は経済的に不可避な現象だということになる。
この理論は、1980年代以降の日本経済の経験と整合的である。プラザ合意以降、円高不況を回避するために実施された金融緩和が土地・不動産市場に資金を流入させ、結果として資産バブルを生んだ。その後、バブル崩壊とともに不良債権処理、金融再編、デフレという過程を経たが、長期的には金利は一貫して低下を続けた。潜在成長率が低下し、人口減少が進む中で、投資先を失った資金が再び不動産に向かうのは、経済構造上の帰結である。この意味で、日本の住宅市場は、「バブル必然理論」がいう「可能なバブル」、すなわち経済の内部論理として生じる価格上昇の均衡状態にあるといえる。
また、この理論は、従来の「バブル=非合理」という理解を根本的に改める。価格が上昇しても、それが制度・人口・金融構造の中で合理的に支えられていれば、崩壊をもたらすとは限らない。むしろ、低金利社会では一定の資産インフレーションが経済の持続性を担保する役割を果たす場合がある。住宅価格の上昇は、金利・成長・人口という三つの長期要因が相互に作用した「構造的高価格均衡」として理解すべきなのである。
ここで重要なのは、住宅市場における均衡が単に供給と需要の一致によって成立するわけではないという点である。住宅価格は、金融政策、都市政策、税制、人口動態、社会心理といった多層的な要因が絡み合う「制度的均衡」である。日本の政策史を振り返れば、1980年代の金融自由化と低金利政策、1990年代の地価抑制策と金融再建、2000年代の都市再生特措法、2010年代の量的緩和、これらはいずれも住宅市場の構造を直接・間接に規定してきた。住宅価格の高止まりは、こうした政策の蓄積によって形成された「政策的均衡」でもある。
さらに、社会心理の側面もこの理論に統合される。住宅価格が長期的に上昇する経験を人々が繰り返し観察すれば、「住宅は下がらない」という期待が定着する。この期待は自己実現的に価格を支える。低金利によって実際に価格が上がり、上がることで再び期待が強化される。この循環が安定的に続くとき、社会全体の信頼構造が住宅市場の基盤となる。つまり、住宅価格は、金融構造と心理構造の両方によって支えられた「信頼の均衡」によって成立している。
このように、ユーザーコスト理論が示す金融的合理性、厚生一貫的理論が示す生活的合理性、バブル必然理論が示すマクロ経済的必然性、そして社会心理が示す信頼のメカニズムが結びつくとき、住宅市場は長期的に安定した高価格均衡を形成する。これが本稿でいう「構造的高価格均衡」である。
したがって、住宅価格の上昇を短期的な政策介入で抑えることは、経済全体の安定を損なうリスクを伴う。むしろ重要なのは、この高価格均衡をいかに持続可能な形で管理するかである。金融政策、都市再開発政策、人口政策、税制を整合的に運用し、期待を適切にコントロールすることが、低金利時代の住宅政策の核心となる。
次章では、この理論的枠組みを実証的に検証する。1986年から2025年にかけての東京住宅市場データを用い、住宅価格、家賃、金利、期待の関係を定量的に明らかにすることで、構造的高価格均衡の存在を実証的に確認していく。